本煤竹箸
ほん すすだけ はし







古民家の一部として人々と営みをともにしてきた煤(すす)竹の箸 時の流れを静かに語るような、ひとつひとつの個性をお楽しみください 和食器との相性も抜群です
日本の原風景ともいえる古民家の家具や内装の一部として使われていた竹。 一般的に多くの竹は時を経て飴色に美しく変化をしますが、さらに囲炉裏からの煙(煤)などで燻(いぶ)され長い時間をかけて深いおもむきある色に変化していきます。
縄で固定されていればそこだけ薄茶色の跡が、灰が多く飛べば黒い模様として跡が、それは古民家で暮らす人々の営み、長い時の流れを「時の名残」として映し出します。
20年以上前に解体された九州福岡県の古民家で使われていた煤竹を寝かせ、できる限り無駄なく「時の名残」を大切にした竹箸として蘇らせました。 当然ですが、年々本物の煤竹の材料は手に入りにくくなっています。今回も限りある材料での制作となります。
何十年、いやもっと長い時間かもしれない古民家で流れていた~静かな時~を、あなたの食卓に引き継いでみませんか。
●お好みの個性のお品を選んでいただけます。「お好みの個性をえらべます」コーナーを確認ください。
★この商品は、送料の安い日本郵便レターパック(520円・ポスト投函)でお送りすることがあります。その場合の送料は当店で変更させていただきます。
*お届け日時の指定がない場合・代金引換・コンビニ決済でない場合に限ります

イメージ写真です
営みや歴史を語るお箸

長い年月をかけて この煙が家屋を虫や腐食から護ってくれます
原材料としての煤竹
古民家で長い月日をかけて色を増してゆく煤竹。 長年囲炉裏から出る煙で燻(いぶ)された家屋は屋根裏や柱までいきわたり建物は美しく堅牢になっていきます。 写真の薪棚の柱の色にご注目。 梯子のような物は、天井から吊るされた火棚と呼ばれる道具で、元来は強い火の粉などから天井を護る板状のものでしたが現在で装飾化してこのような形になったとの事。火棚の中央下から竹が伸びていますが、これに自在鉤(かぎ)と呼ばれる鉄瓶などを吊るす道具が提げられます。
一般的に真竹が使われる事が多いのですが、この本煤竹箸の元となる生活史を物語る竹の色・形・そして模様は千差万別。 ひとつひとつから使える部分を慎重に吟味して、洗浄・切断・成形・研磨・塗装(数回)して出来上がります。
*このページの家屋や古民家の風景などは、私と私の気の置けない友人たちが撮影した群馬県や富山県の古民家の姿です。 竹材は実際に今回の箸に使われた一部です。
 竹だけではなく木材の柱もご覧の通りの黒光り
イメージ写真です
竹だけではなく木材の柱もご覧の通りの黒光り
イメージ写真です  囲炉裏(いろり)の上の火棚 灰と煤をかぶっています
イメージ写真です
囲炉裏(いろり)の上の火棚 灰と煤をかぶっています
イメージ写真です  今回のお箸の材料である煤竹
今回のお箸の材料である煤竹 
個性の面白さ
時間や場所によって様々な表情の原料(竹)が残さるために、生まれる竹箸の色も様々。 もちろん同じ形デザインと大きさに統一されています。 ひとつひとつの模様をじっくりと味わいながらテーブルで思いを馳せるのもきっと素敵な時間になるのではないでしょうか。
 節なし
節なし 
お好みの「個性」を選べます
煤竹のどの部分を使うかによって表面の個性があります。 そこで、可能な限りグループ分けしております。 「カートに入れる」ボタンをタップしてご選択ください。
お写真はおよそのイメージです。個別の指定は承っておりません。あらかじめご了承ください。
商品ボタンが表示されない場合は「売り切れ」です。
節なしA
縄などの跡のコントラストが比較的はっきりしています。


節なしB
全体的にノーブルなグラデーションです


節ありC
比較的ノーブルですが、肌合いに多少個性があります。


節ありD
cよりコントラストが比較的はっきりとしています。 肌合いは同じく少し個性があります。


節ありE
全体のグループ分けで最も煤竹らしい個性があります。 斑紋とグラデーションにご注目ください。


形デザインのお話し
竹らしい四角いデザイン
「竹を割ったような・・・」という比喩がありますが、竹箸はエッジの効いた四角のデザインが似合います。 角がありますので転がりにくく、麺なども滑りにくいという特徴があります。
四角の箸は、決して持ちにくいとは思いませんが、六角形や丸いお箸には勝てないというのが正直な印象です。 先代の民芸店時代から多くのお箸を取り扱ってきましたが、持ちやすさ・転がりにくさ・堅牢さ・見た目の美しさなどすべて一長一短。 まるで私たち人間のようでなんだか微笑ましく感じます。


雰囲気や好みで選ぶ二つの竹箸
形のデザインとして、竹の節(ふし)の部分を使った「節あり」と「節なし」の二種類をご用意しました。もちろん「好み」が一番大切なのですが、テーブルによって使い分けしていただくのが理想的ですね。
シンプルスタイリッシュな「節なし」
シンプルデザインな食器などを中心とした比較的スタイリッシュなテーブルには「節なし」のお箸をおすすめします。



 裏の姿です(節なし)
裏の姿です(節なし) 和の雰囲気と高級感ある「節あり」
存在感ある土物和食器を多く使う比較的「和」の雰囲気を大切にしたいテーブルには「節あり」をおすすめします。 懐石料理などにぜひどうぞ。


 竹の姿を想像できるデザイン
竹の姿を想像できるデザイン  裏の姿です(節あり)
裏の姿です(節あり) 塗装について
商品名「木固めエース」および専用仕上げ剤(ウレタン)
検査適合基準食品衛生法:器具・容器包装規格(370号)溶出試験に適合
多くの木工食器に使われている比較的安全な塗装です。
煤竹の表情を見ていただくには拭き漆でも可能ですが、耐久性にかなり難があります。 そこで、比較的安全で耐久性に優れ、広く使われているウレタン塗装仕上げにしました。 (漆塗で耐久性を上げるには、当店の木製漆箸のように何回も重ね塗りをしなければいけません。重ね塗りをすれば素材の表情は見えにくくなります。)
少しでも長くご愛用頂く為に食洗機や乾燥機はお避けいただき、スポンジ洗浄後の自然乾燥をお願いしております。
どんな事でもご質問大歓迎!店主や女将にお聞かせください
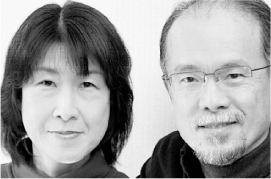
同じ大きさや形の和食器
SAME SIZE ITEM最初のレビューをお書きください。 “本煤竹箸”
レビューを書くには、会員登録しログインしていただく必要がございます。
会員登録/ログインはこちらから
本煤竹箸
ほん すすだけ はし









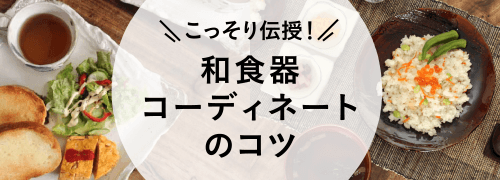

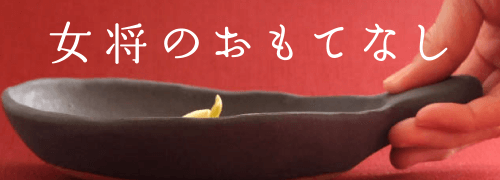
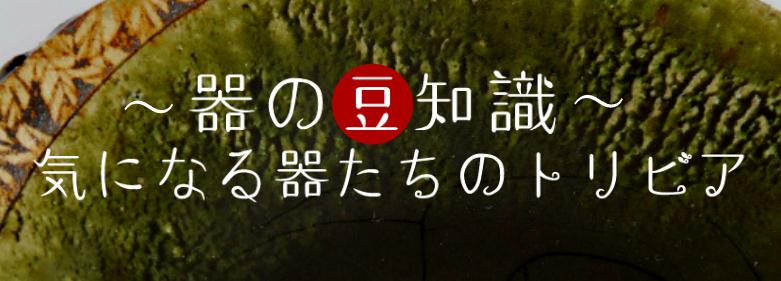










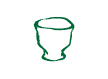

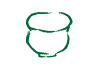


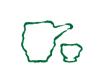



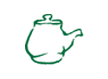
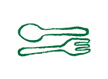


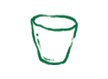



























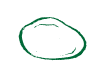
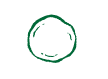
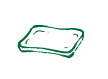
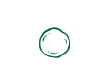

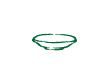
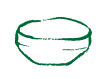

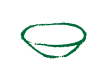
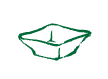

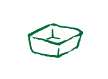

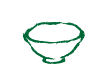
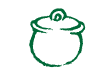



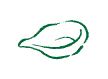
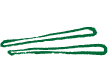
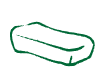
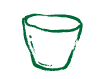

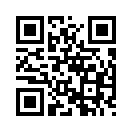



 閲覧履歴
閲覧履歴
Reviews
まだレビューがありません。